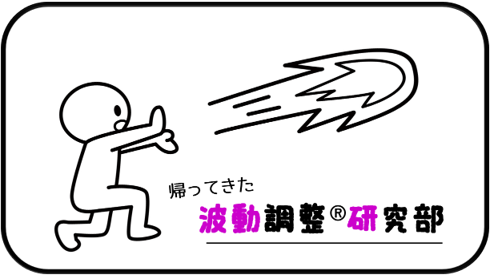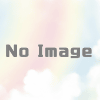人生の映画を抜けて
いつもありがとうございます。
True Natureを生きる波動調整®です。
本日も全身全霊でお伝えしてまいります。
私たちが観ているもの
私たちが観ている現実
私たちが体験していると
思い込まされている現実
これはよく映画に例えられます。
映写機から出た情報が
映し出されたスクリーン
そこで時間とともに流れる
学さんの世界という名の映画
波動調整®というのは
観ている映画の中に取り込まれずに
観ている自分の側に気づいてること
それは頭の中で納得させるものではなく
身体で腑に落としていくことがとても重要です。
映画という現実ドラマの中の
キャラクターに没頭してしまう、
その中の世界で問題解決に奔走する。
そうではなくて
その観ている世界が世界のすべてではないこと
そこを離れた視座で世界を観ていくことで
その問題が問題ではなかったことに気が付けるのです。
波動調整®は問題を解決するためではなく、
目の前の問題と取っ組み合うことではなく
問題が問題の本質でないことに気づくです。
まずは目の前の映画をただ観てみましょう。
ただ観るというのは余計な色をつけないことです。
ただ流れるその映画を映画として観ることです。
映画の中の映画に落ちる
このように世界を映画に例えると
大きな勘違いに落ちる人がいます。
では目の前の映画を
自分の好きなフィルムに
切り替えたら良いのですね?
この発想が極めて危険だということに
気が付いている方はどれだけいるでしょうか?
好きなものだけを見ればよい。
フォーカスを変えれば現実が変わる。
ポジティブでいれば引き寄せが起きる。
良いイメージで現実が創り出せる。
これは結局のところ
観ている映画をどうにかしようと
しているに過ぎないということです。
映画の外側の世界に出ているわけではなく
映画のキャラが映画を観ようとしているだけ。
映画の中の映画に取り込まれてしまう。
仮想世界の中の仮想世界にハマっていく。
幻の中で幻をいくら積み重ねても
より幻影が強化されていくだけなのです。
確かに映画の中の映画は居心地が良いのです。
しかしながらキャラクターが
映画の中で映画を造り出し続けていると
何が映画なのか区別が出来なくなってしまい
その世界から出てこれなくなっていってしまいます。
(現実を自由自在に書き換えているようで
悪い幻にハマり込む人はよく見受けられます。)
このように自我の目線の造物で
マトリックスを強化していくことが
波動調整®でいう退化の方向性です。
波動調整®はその幻を見破っていくこと。
仮想の映画を抜けていくための取り組みです。
その初めのステップは
余計なものを造り出そうとしてしまっている
その自分に気づいて止めていくことからです。
映画を抜ける
波動調整®は何をするかといえば
“していることを止める"ことです。
それはつまり
映画の中で映画を造ろうとすること
映画の中で問題解決に取り組むこと
これを止めていくということです。
そして"ただ観る"を実践すること
つまり余計な色付け・フィルターを
通さずに本来の映画をきちんと観ること。
そして映画を観ている側の
自分に気づいていくことです。
映画を観ていることに気づけば
映画を観ていることを
止めることができるということです。
映画の中にいるキャラクターは
映画を止めることはできません。
この違いは極めて大きな違いです。
波動調整®は
『本当のわたし』を思い出すことです。
それは映画を抜けて
映画を観ている自分に気づくことであり
さらにいえばその自分の世界をも超えて
意識を進化させていくことが目的です。
向いている方向性は壮大なスケールでありながら
していく取り組みは目の前をきちんと観ていくという
具体的で地道な純粋な探求の道が波動調整®です。
ぜひ目の前の現実映画に気づいた方から、
映画の中の映画の矛盾に気づいた方から
波動調整®という取り組みの真の意味に
気づいて頂けるものなのだと感じています。
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。